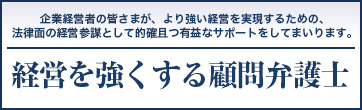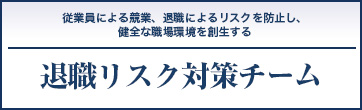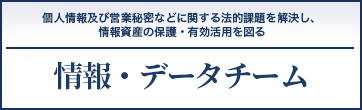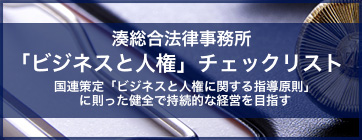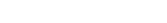遺言がない場合の会社支配権の帰趨
タイトル..
遺言がない場合の会社支配権の帰趨
ご相談
私の父親は、XYZ精機株式会社の創業者で、設立以来父親が代表取締役を務め、自社株(200株)もすべて保有していました。父親と母親との間には、私と、弟がおります。残念なことに、父親と母親の夫婦仲は悪く、長年別居状態にありました。また、私が後継者と目されて特別扱いを受けてきたこともあって、私と弟の仲も悪く、弟は母親になついていました。
私は、大学卒業後は経験を積むため電機会社に就職していましたが、数年前にXYZ精機に入社し、その際に、父親から株式の40%(80株)の贈与を受け、同社の取締役に就任しました。
しかし、その後しばらくして父親は、認知症を発症し、経営から身を引くこととなり、取締役会にも株主総会にも出席することができなくなってしまいました。
私は、取締役の任期満了を迎え、取締役再任のための株主総会を開催しなければならなくなりました。そこで、議事録上は父親が株主総会に出席して議決権を行使した形にして、私を取締役に再任し、取締役会も現実には開催せずに議事録を作成するだけで、私を代表取締役として選任して経営を続けてきました。
その後10年近く経営してきたところ、遂に父親は死亡し、相続が発生することになりました。
そうしたところ、母親と弟から私宛に内容証明郵便が届きました。そこには、実際に株主総会も取締役会も開催していない以上、私は代表取締役としての資格を有していないこと、また、株主総会で、相続財産となっている株式120株全部を母親と弟が行使して、弟を取締役として選任し、取締役会を開催して弟を代表取締役に就任させると書かれていました。そんなことが認められるのでしょうか?
回答
1 株式は遺言がない限り、相続人間の「準共有」となります
(1) 遺言がない場合には、後継者が会社支配権を得られない事態となる
相談者は、父親の死亡時に、全株式である200株のうち、その40%に当たる80株を有していました。そして、相談者は4分の1の法定相続分を有していますから、父親の遺産である株式120株のうち、4分の1に当たる30株を相続でき、過半数の株式(80株+30株=110株)を取得して、会社支配権を獲得できるようにも思えます。
しかしながら、株式については、各相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるわけでありません。株式の相続が発生した場合には、遺言がない限り、遺産分割協議により誰が株式を取得するのかを決める必要があり、それが決まるまでは、株式は相続人間で準共有になります。
相談者は、相続が開始されると、株式は法定相続分にしたがって当然に分割されるものと思い込んでいたのですが、安易な思い込みにより、相談者の持株比率は過半数にすら届かず、会社支配権を得られないという状況になってしまいました。
(2) 準共有の株式全株の株主権の行使は、持分の多数決で決まる
準共有の場合、各相続人は、準共有状態にある株式全体に対し、各人の法定相続分に応じた持分を有するに過ぎません。準共有の株式の株主(株式の準共有者)が、株主総会で議決権行使をするためには、そのうち1名を権利行使者として指定し、決定した権利行使者を会社に通知する必要があります(会社法106条本文)。そして、この権利行使者の指定は、共有物の管理方法として、準共有持分の過半数で決めることになります(民法252条1項)。
ご相談者の場合、父親の相続財産である株式120株について、母親、相談者、弟とで、その法定相続分に応じ、2:1:1の持分を有する状態になりますから、母親と弟が結託すれば、4分の1の持分しかない相談者は多数決に敗れ、120株全株について株主権を行使できないことになります。
そうすると、相談者は80株しか株式を有していませんから、株主総会を開いても、120株の議決権を行使できる母親・弟に敗れ、会社支配権を喪失することになります。
この状況を打開するためには、相談者が母親・弟との遺産分割協議で、株式の過半数を取得できるよう交渉するしかないのですが、母親らも相談者の窮状につけ込んで、株式を評価額よりはるかに高い価格で買い取るよう求めてくる可能性もあり、協議が難航することは必至です。
(3) 後継者が全株式の過半数を取得できる遺言を作成することが必要
このような事態を避けるには、父親は、相談者が全株式の過半数以上(できれば3分の2以上)取得できるように、株式を譲渡しておくか、遺言書を作成しておくべきだったと言えます。遺言があれば、株式は準共有状態にはならず、遺言書に定めたとおりに相続されます(ただし、他の相続人の遺留分に留意して対策を講じておく必要があります)。
なお、遺言をするためには、遺言者に遺言内容を理解できるだけの事理弁識能力(遺言能力)が必要ですが、仮に認知症が発症している場合には、この能力に疑義が生じることも考えられます。もっとも、たとえ後見開始の審判を経た後でも、その事理弁識能力が回復したときは、医師2人以上の立ち会いのもとに遺言をすることはできるとされています(民法973 条)。したがって、仮に認知症により事理弁識能力を欠くに至った場合であっても、後のトラブルを避けるためにも、状況をみて可能な限り遺言を遺すようにしておくことが重要です。
2 後継者を取締役にするためには適法な株主総会決議が必要です
(1) 適法な株主総会決議がない場合の帰趨
次に、父親が認知症になって株主総会に出席できなくなった後は、実際には株主総会を開催していないため、株主総会決議は不存在であり、後継者の相談者は、適法な取締役とはいえません。また、仮に形だけ株主総会を開催していたとしても、株主総会の決議は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う」こととされていますから、株式の60%を持つ父親が出席しなければ定足数を満たさず不適法です。さらに、仮に父親が株主総会に実際に出席していたとしても、父親が認知症のため意思能力が欠如している状態では、議決権を行使できませんから、やはり不適法となってしまいます。
したがって、相談者は、適法な株主総会決議によって取締役に選任されておらず、法律上は取締役とは言えないのです。父親の死亡後、もし相続人の母親や弟から株主総会決議不存在確認の訴え、取締役の地位不存在確認の訴え等を提起されれば、相談者は敗訴し、相談者が取締役ではないことが明確になります。取締役でない以上、相談者は経営から排除されてしまうでしょう。
(2) 保佐・後見等の申し立ての検討
上記のような状況に陥ったのは、父親が認知症になって、株主総会に出席できなくなったにも拘わらず、そのまま放置して、適法な株主総会を開催しなかったことが原因です。
このような事態を避けるためには、父親の認知症の進行度に合わせて、保佐・後見(場合によっては補助)の申立てを行うことが必要です。
会社と取締役の法律関係は委任契約ですので、裁判所が後見開始の審判を行った場合は、委任契約が終了し(民法653条3号)、取締役は退任となります。補助の場合は、委任契約は直ちに終了とはなりませんが、こうしたケースも想定して、定款等で取締役の終了事由として定めておくことも検討課題といえます。
なお、令和3年(2021年)3月1日施行の会社法改正によって、会社法331条1項2号が削除され、成年被後見人も取締役に就任することができるようになったことに留意が必要です。
相談者のケースでは、その後、適法に株主総会を開催して、相談者を取締役に選任する決議をすることが必要です。後見人等には、その代理権に基づき、株主総会において父親本人の代わりに議決権を行使してもらい、相談者を取締役に選任します。
なお、成年後見人は当然に法定代理権が付与されますが、補助人・保佐人・任意後見人は当然には代理権が付与されません。補助・保佐であれば、家庭裁判所に株主総会における議決権行使の代理権を付与するよう申立てておくことにより、その代理権に基づいて議決権を行使することができます。
相談者が取締役に選任された後、取締役会を開催して、相談者を代表取締役に選定すれば、相談者は名実ともにXYZ精機の適法な代表取締役に就任することができます。
3 結論
今回のケースでは、相談者が父親の生前にきちんとした事業承継対策をしていなかった結果、母親と弟から足元をすくわれる結果となってしまいました。これは、株主総会や取締役会など開かなくても大丈夫という思い込み、株式は法定相続分にしたがって当然に分割されるという思い込みがあったからです。
事業承継にはさまざまな落とし穴がありますから、意図しない事態に陥らないためにも、常日頃から弁護士に相談することが重要です。
-300x72.png)
事業承継の関連ページ
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



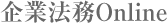
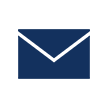 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは