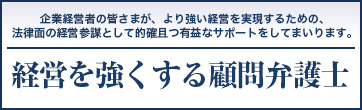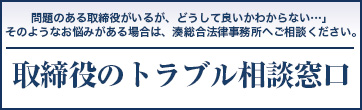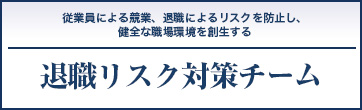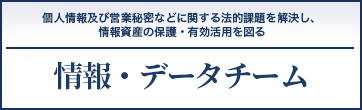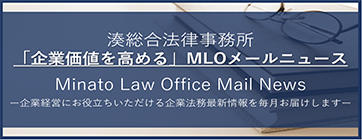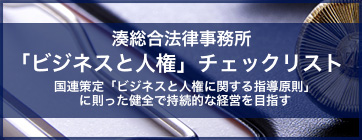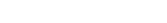適格消費者団体による差止請求
タイトル..
適格消費者団体による差止請求
一般的に、事業者と消費者との間の契約金額は小さく、薄利多売というビジネスモデルになっていることが多いといえます。
悪質な商法を行う事業者も同様で、被害にあった消費者は損害額が大きくないことから、訴訟等の法的解決手段は費用倒れとなってしまい、権利回復し難いという問題があります。
また、同一事業者との消費者紛争は同じ争点となることがほとんどです。
そこで、同種の紛争の発生及び拡大を未然に防止し、消費者の利益を擁護するため、一定の要件を満たした適格消費者団体が事業者の不当な行為を差し止めることが認められています。
なお、平成28年10月からは、このような差止請求制度に加えて、多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、消費者団体が訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度(いわゆる日本版クラスアクション)も設けられました。
(1)適格消費者団体
消費者全体の利益の擁護のために差止請求権を適切に行使する専門性等が備わっていると内閣総理大臣が認定した団体のみが適格消費者団体として認められます。
適格消費者団体として認められるためには以下の要件等を満たす必要があります。
・消費者被害の救済のための相当の活動実績を有すること
・被害事案について分析したり、法的な検討を行ったりする専門性を備えていること
(2)差止請求の対象
消費者契約法に定められた事業者の不当行為、すなわち、不当な勧誘行為や不当な契約条項を含む契約の締結が不特定多数の消費者に広がる可能性がある場合には差止請求の対象となります。
不当な勧誘行為の例としては、不実の告知、不退去、断定的判断の提供などが挙げられます。
また、不当な契約条項を含む契約締結の例としては、消費者が支払うべき違約金等の額を過大に設定する条項、事業者の損害賠償責任を免除する条項などが挙げられます。
(3)差止請求の要件
差止請求が認められるのは、「事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法等に違反する不当な行為を行っている、又は行うおそれがあるとき」とされています。これは、事業者の不当な行為により、特定されていない相当数の消費者に対して被害者が拡散する蓋然性がある場合を指します。
「おそれがあるとき」と規定されていることから、不当な行為がなされる蓋然性が明らかになれば足り、現に不当な行為をしていなくても差止の対象になります。
(4)差止請求の効果
差止請求が認められる場合、適格消費者団体は、当該不当行為の「停止又は予防に必要な措置」をとることを請求できます。不当勧誘行為の停止を求めることはもちろん、「予防に必要な措置」として、勧誘マニュアル等の不当行為に共用された物の廃棄を求めることができることもあります。
また、差止訴訟で適格消費者団体が勝訴したにもかかわらず、事業者が差止判決に従わない場合には、間接強制の方法による強制執行がされる可能性があります。
この場合、差止判決に従わない事業者は、執行裁判所から、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を適格消費者団体に支払うよう命じられることになります。
適格消費者団体に関する対応でお困りの場合は是非一度当事務所にご相談ください。
消費者問題の関連ページ
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



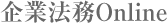
-300x72.png)
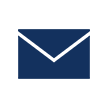 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは