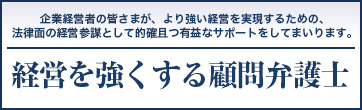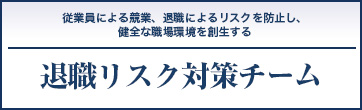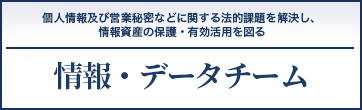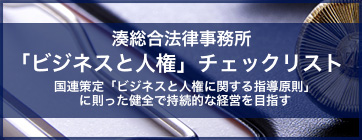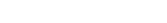判例研究
「経営判断原則、信頼の原則」について研究しました。
令和4年10月12日(水)「経営判断原則、信頼の原則」について研究しました。
| 日時 | 令和4年10月12日(水) |
|---|---|
| 場所 | 湊総合法律事務所 |
| 報告者 | 弁護士 久保 真衣子 |
| 内容 | 「経営判断原則、信頼の原則」について研究しました。 |
第399回 判例・事例研究会
日時 令和4年10月12日
場所 湊総合法律事務所
報告者 弁護士 久保 真衣子
【判例】
| 事件 | 大阪地方裁判所令和4年5月20日判決 |
| 事件の概要 | 大手ハウスメーカーである補助参加人が、真の所有者からC株式会社が本件各不動産を買い受けたことを前提に、同社との間で本件各不動産を代金70億円で買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、手付金として14億円、更に残代金として約49億円を支払ったが、実際には本件各不動産の真の所有者はC株式会社に本件各不動産を譲渡しておらず、本件売買契約に係る取引は詐欺グループが仕組んだ架空の取引であったことについて(以下「本件詐欺事件」という。)、補助参加人の株主である原告が、本件詐欺事件当時、補助参加人の代表取締役であった被告 A 及び取締役であった被告 B には、それぞれ取締役としての善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があり、そのために本件詐欺事件により補助参加人に55億5900万円の損害が生じたとして、被告らに対し、会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき、各自55億5900万円の支払いを求める株主代表訴訟の事案。 |
| 今回取り上げる争点 | 取締役の任務懈怠責任 |
| 条文 | 会社法423条1項 1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株主会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負いう。(2項以降は省略) |
| 判旨(一部) | 2 争点1(被告A1に関する任務懈怠責任の成否)について ⑴ ①経営判断(本件稟議書の決裁及び残代金決済前倒しの了承)の誤りについて ア(ア) 本件では、上記1⑶のとおり、代表取締役であった被告 A による本件稟議書の決済を経て、補助参加人による本件各不動産の購入が決定され、その結果、補助参加人に多額の損害が生じたものである。 しかるところ、取締役による決済を経て不動産を購入するに至ったが、 それによって当該会社に損害が生じた場合、かかる意思決定に関与した取締役が当該会社に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うか否かについては、取締役に求められる上記の判断が、当該会社の経営状態や当該不動産の購入によって得られる利益等の種々の事情に基づく経営判断であることからすれば、取締役による当時の判断が取締役に委ねられた裁量の範囲に止まるものである限り、結果として会社に損害が生じたとしても、当該取締役が上記の責任を負うことはないと解され、当該取締役の地位や担当職務等を踏まえ、当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものである場合には、かかる事実等による判断の推論家庭及び内容が著しく不合理なものでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはないというべきである。 (イ) そして、会社によっては、その組織の規模等のために、各種の業務を種々の部署で分担し、その部署に治験や経験を集積して、権限も適宜委譲することによって、専門的知見を要する業務も含めて広汎な各種業務に効率的に対応することを可能とするものであり、当該会社がこのような大規模で分業された組織形態となっている場合には、取締役がこれらの各部署で検討された結果を信頼してその経営上の判断をすることは、取締役に求められる役割という観点からみても、合理的なものということができる。そうすると、当該会社が大規模で分業された組織形態となっている場合には、当該取締役の地位及び担当職務、その有する知識及び経験、当該案件との関わりの程度や当該案件に関して認識していた事情等を踏まえ、下部組織から提供された事実関係やその分析及び検討の結果に依拠して判断することに躊躇を覚えさせるような特段の事情のない限り、当該取締役が上記の事実等に基づいて判断したときは、その判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程は合理的なものということができる。 イ 本件稟議書の決裁について (ア) 補助参加人の規模及び被告Aの地位等 補助参加人は、上記1⑴及び⑵のとおり、単体の売上高が1兆円を超え 従業員すうも1万4000人を超える経営規模の極めて大きな会社であり、その組織形態についてみても、組織的な事務分掌の定めや役職を置いて業務を分担させ、その分担状況に応じて権限も委譲され、具体的な事務内容やよるべき手続についても定められていた。このように、補助参加人は、大規模で分業された組織形態となっていたということができる。そして、被告Aは、上記1⑴イのとおり、このような補助参加人において、最高執行責任者(COO)として、その各部門の業務を総合運営し、業務執行全般を指導統制することなどが求められていた代表取締役社長であったのであり、補助参加人において販売用不動産の購入について被告Aの決裁が必要であるのは購入総額10億円いじょうのものであったことからみても、補助参加人において被告Aの判断に求めていたのは、多額の資金を要する不動産購入について経営全体を総括する立場からの検討であり、個別の契約内容を具体的に点検することを求めていたものではないといえる。 (イ) 事実等の認識ないし評価に至る過程について a そこで、被告Aの認識していた事実等について更に検討すると、被告 Aは、本件稟議書を決裁し、その際に本件稟議書の内容を確認することができたが、本件稟議書に記載されていた事項は上記1⑶キのとおりであり、いずれの点においても、これに依拠して判断することに躊躇を覚えさせるようなものではなかった。 本件各不動産の所有者(補助参加人が転売を受けるC株式会社に対する 譲渡人)であるIの本人性について、上記1⑶ウのとおり、GやFらも含めて東京マンション事業部等の担当者は、偽Iが本件各不動産の所有者である I本人であることの信用性は高いと考えており(なお、Gらは、公証人が旅 券等の提出により面前のIが人違いでないことを確認したなどとする公正証書を根拠について、Iの本人確認の信用性は高いと判断したのであり、その判断が当時のものとして不合理なものであったということもできない。)、したがって、本件稟議書にも、その信用性に疑義を生じさせるような事情は一切表れていない。 また、被告Aは、現地を視察し、その際、上記1⑶カのとおり、Fから 本件各不動産についての説明を受けているが、その説明内容に不自然ないし不合理な点があったということもできない。 上記1⑶キのとおり、本件稟議書の冒頭の「はじめに」では、株式会社 CがIと平成29年4月3日付けで本件各不動産の売買契約を既に締結している旨の記載があるが、本件稟議書の「契約の相手」欄では、契約の相手として株式会社Cが記載されていたのを、手書きでC株式会社と訂正されており、補助参加人に対する本件各不動産の譲渡人の記載に矛盾があるかのような記載がされている。しかし、被告Aは、上記1⑶カのとおり、マンション事業本部長であったFから、直後に、既に本件各不動産の所有者であるIと株式会社Cとが契約を結んでいるが、改めてIと同社が契約を締結し直し、同時に同社と補助参加人とが契約を締結して本件各不動産を取得すると聞いていたのであるから、本件稟議書上は(その時点では、株式会社Cとの間の締結済みの契約書が存在する。)、株式会社C(訂正前)ないしC株式会社(訂正後)が契約の相手方として記載され、かつ、本件稟議書上の契約の相手方の記載に訂正(それも、いわゆる前株か後株かの違いという類似した商号の会社間での訂正)があったとしても、本件稟議書に依拠して判断す ることに躊躇を覚えさせる次条があった(したがって、被告Aとしては契約の内容を担当者に再度確認等すべきであった)などということはできない。 ・・・ (ウ) 判断の推論過程及び内容について 上記1⑶ケのとおり、被告Aは、本件稟議書の内容、現地視察の際に直 接得た印象、その際にFから受けた説明内容に基づき判断をしている。 そこで、かかる事実等による被告Aの判断の推論過程及び内容の合理性 について検討すると、上記の本件稟議書の内容やFの説明内容等からは、C株式会社を通じて本件各不動産を購入する偽Iが真実は本件各不動産の所有者ではなかったという事情は一切うかがわれないのであり、かかる事実等により本件各不動産を真の所有者から購入することができると考えた被告Aの判断の推論過程及び内容に不動里というべき点はない。 本件各不動産の購入に要する費用は、C株式会社に支払う売買代金だけ で70億円を要するものであったが、当時の補助参加人の規模や売上高当に鑑みれば、購入につき特に問題となる金額ではなく、また、本件各不動産はJR●駅から徒歩約4分の距離に位置するマンションの建設が可能な約600坪のまとまった土地で、頻繁に市場に現れるような土地ではなく、本件稟議書からは採算性についても特段の問題はなかったのであるから、本件各不動産を購入するとした判断についても、何らの不合理な点は見当たらない。 (エ) 以上のとおり、本件稟議書を決裁した被告Aの判断は、その前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものであり、かつ、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著しく不合理なものではなかった のであるから、経営判断として同被告に許された裁量の範囲に止まるものであったということができ、被告Aが、本件稟議書を決裁したことを理由に善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うということはできない。 ウ 残代金決済前倒し了承について (ア) 事実等の認識ないし評価に至る過程について ・・・ (イ) 判断の推論過程及び内容について ・・・ (ウ) 以上のとおり、残代金決済前倒しを了承した被告Aの判断は、その前提となった事実等の認識ないし評価に係る過程が合理的なものであり、かつ、かかる事実等による判断の推論家庭及び内容が著しく不合理なものではなったのであるから、経営判断として同被告に許された裁量の範囲に止まるものであったということができ、被告Aが、残代金決済前倒しを了承したことを理由に善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うということはできない。 ⑵ ②従業員に対する監視監督義務に係る任務懈怠について ……しかし、被告Aは、上記1⑴イのとおり、補助参加人の最高執行責任者(COO)として、その各部門の業務を総合運営し、業務執行全般を指導統制することなどが求められていた代表取締役社長の立場にあったのであり、被告Aには、それを前提とした役割が期待されていたのであるから、当然に個別の従業員に対する関係において監視監督に係る具体的な注意義務を負っていたということはできない。 そして、上記⑴等で認定説示した被告Aの認識した事実等を前提に考えても、被告Aには十分な本人確認が行われていたことを示す情報ももたらされており、また、本件各不動産の所有者本人と称する者から売買をしていない旨の通知書は届けられていたものの、これは偽Iの本人性に疑義があることを示すものではなく、妨害工作である可能性が高いことを示す検討結果も示されていたこと、そして、これらの事実等が大規模で分業された組織形態となっている補助参加人において組織的に検討した結果としてもたらされたものでもあって、代表取締役であった被告Aがこれらの事実等を信頼して判断することも合理的なものであったこと(上記⑴参照)に照らせば、C株式会社に本件各不動産を譲渡する売主の本人確認も含め、被告Aに原告の主張する監視監督義務があったということはできない。 ⑶ ③内部統制システム(リスク管理体制)構築義務に係る任務懈怠について ・・・ エ このように、補助参加人の内部統制システム(リスク管理体制)が実効的に機能していなかったということはできず、したがって、被告Aに、原告の主張する、本件取引が中止されるような内部統制システム(リスク管理体制)を構築すべき義務があったということはできない。 ⑷ ④被害回復措置について ・・・ ⑸ ⑤被害拡大防止措置について ・・・ |
以上
ご相談のご予約はこちらから



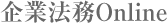
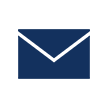 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは