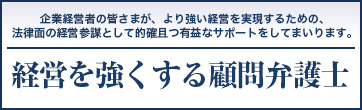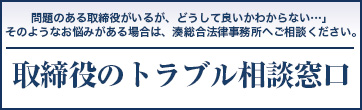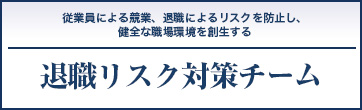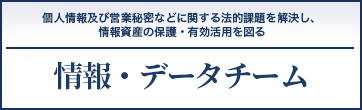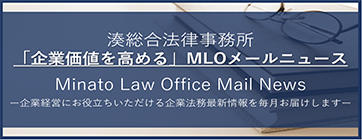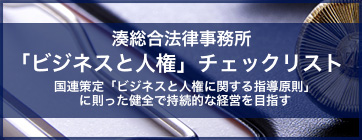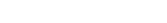退職勧奨の進め方とポイント
タイトル..
退職勧奨の進め方とポイント
Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
A:これまで見てきたとおり、解雇という方法は、相当ハードルが高く、会社にとってもリスクが大きいことから、解雇の要件を満たしているかどうかについて疑義があるときは、退職勧奨を実施し、従業員に任意の退職を促していくのが穏当な方法となります。
実際に退職勧奨を進める場合の大まかな流れとポイントは次のとおりです。
(1)退職勧奨の方針・理由を社内で共有し、退職時の処遇を確認する
退職勧奨を実施する理由や当該従業員に対してこれまで会社が行ってきた指導・対応を確認し、直属の上司からの聞き取りなども行った上で、会社として退職勧奨を実施するという方針を確認します。
従業員が退職に応じやすいように、退職の際に一定の処遇(退職金の上乗せ、転職サイトの利用費用の負担、転職先や転職エージェントの紹介など)を提示することも考えられますので、この点についても社内でよく確認しておきましょう。
(2)面談担当者のための面談メモを作成する
実際に退職勧奨を実施する場合、面談担当者にもプレッシャーがかかります。
面談の途中で何を言うべきか、頭が真っ白になるということも十分あり得ますので、退職勧奨の理由などを記載した面談担当者用のメモを作成しておきましょう。
退職勧奨の際に言ってはいけない言葉や注意点などを記載しておくことも有用です。
(3)従業員と面談を実施し、退職してもらいたいという会社の意向を伝える
他の従業員に知られないように、会社の会議室等で面談を実施します。
退職勧奨の理由に制限はありませんが、従業員に納得して退職してもらうことが重要ですので、(1)で確認した退職勧奨の理由を具体的に説明するように心掛けましょう。
(4)退職勧奨に応じるか否かについて検討する期限を伝え、検討を促す
初回の退職勧奨で、その場で決断を迫ってはいけません。
従業員が十分に検討した上で決断できるような期間を設定し、次の面談の日程を伝えます。
家族がいる場合には、週末に相談できるように週末をはさんだ日程を提示しておくという配慮をするとよいでしょう。
(5)退職の時期、退職時の処遇などを話し合う
従業員側の事情によって、会社提案の退職日を1か月後ろ倒ししてもらいたいという希望や、会社が提案した退職時の処遇について要望が出る場合もあります。
すべての要望に応じることは難しい場合でも、円満に退職してもらうことを前提に、退職の時期や退職時の処遇についてきちんと話し合いましょう。
(6)退職届の提出または合意書の作成
従業員が退職に合意した場合には、退職届を提出してもらうか、雇用契約の終了に関する合意書を作成します。解雇ではなく、従業員の意思に基づく退職であることを証する重要な書類になりますので、必ず提出・作成してください。
合意書の文言などについて分からない場合には、弁護士にご相談ください。
解雇・退職勧奨に関する問題について湊総合法律事務所がサポートできること
当事務所は、主に使用者側の立場で、解雇・退職勧奨に関するご相談、紛争が生じた場合の交渉・訴訟を数多く取り扱ってきました。具体的には、以下のようなサポートが可能です。
(1)解雇・退職勧奨を行う前のアドバイス
解雇をした場合に有効となり得るか、後から無効と判断されるおそれはないかなど、そもそも解雇することが妥当であるかについてアドバイスを行います。また、解雇を行う際には適切な手続を採ることも重要ですので、各事案に応じて、解雇方法や解雇に至る流れについてもアドバイスをさせていただきます。
解雇が難しい場合には、退職勧奨にて退職を促すことも多いですが、退職勧奨の方法が行き過ぎたものであるなど不適切な場合には、違法な退職勧奨として慰謝料請求の対象となったり、退職自体が無効となるなどのリスクがあります。そこで、退職勧奨を行う際にも、事前に気を付けるべき事項についてアドバイスいたします。
(2)解雇・退職勧奨後の紛争解決
解雇や退職勧奨の後に、解雇の要件を満たさず無効である、違法な退職勧奨であったため退職を撤回するなどの主張が元従業員からなされることがあります。
会社との話し合いで解決できそうな事案の場合は、会社で対応する場合のアドバイスを提供するほか、既に元従業員側に代理人弁護士がついている場合など当事者同士の話し合いが難しいと思われるケースでは、当事務所の弁護士が代理人として交渉・訴訟対応を行い、適切な解決を図ります。
裁判となった場合に解雇が有効として認められるかについては、具体的なケースにおける様々な事情をふまえて判断されるため、弁護士でなければ判断が難しいといえます。この判断を誤って安易に解雇してしまった場合、解雇無効を主張されることによりその紛争が終わるまで出勤しない元従業員の給与相当額を支払い続けなければならないといった事態や、元従業員が職場復帰することにより他の従業員にもその事情が知られることになり、会社全体の士気が下がるなどの事態も生じ得ます。
このような事態を避けるためにも、解雇・退職勧奨を行う前、また行った後にトラブルが生じた際には、是非、当事務所にご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
退職方法に関するご相談
2.会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか。
3.本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また、「試用期間」や「採用内定」についても教えていただけますでしょうか。
4.従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか。
6.退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか。
7.退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか。
書籍のご案内
| 従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務 ~予防&有事対応~ 【編者】湊総合法律事務所 【出版社】中央経済社  ◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆ ◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆第1章:競業によるリスク 第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク 第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク 第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク▷詳しくはコチラをご覧ください。 |
退職リスク対策の関連ページ
- 退職リスク対策チームよりご挨拶
- 不正競争防止法の「営業秘密」とは
- 営業秘密の漏洩に対する法的措置
- テレワーク下における秘密情報の管理について
- 退職後の紛争防止のための書式集ダウンロード
- 競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プラン
- 【退職リスク・競業避止における業種別対応のご案内】
- 情報通信業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 不動産業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 旅行業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 介護業・福祉業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 理容・美容業における退職者とのトラブルへの対策・対応
- 【競業避止及び秘密情報に関するご質問】
- 退職者による顧客情報・機密情報の持ち出しへ会社が取るべき対抗措置とは?営業機密トラブルへの損害賠償
- Q.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。
- Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。
- Q.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- Q.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。
- Q.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。
- Q.在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 【解決事例】妊娠・出産に関するハラスメントを早期解決した事例
労務問題の関連ページ
- 労務問題
- 採用内定の取り消し
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 労働条件の不利益変更
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- セクハラ被害を申告されたら
- パタニティ・ハラスメント対策
- 自宅待機命令と賃金支払義務
- 起訴休職処分
- 解雇紛争の予防と対処
- 従業員を解雇できる場合とは
- 売上の減少に伴い整理解雇を行うには
- 解雇と退職勧奨
- 退職勧奨の進め方とポイント
- 退職勧奨の面談時における留意点
- 退職勧奨が違法となる場合
- 解雇の要件とは
- 有期労働者の無期契約への転換
- 退職後の競業避止義務について
- フリーランスと競業避止義務
- 労務問題に関する当事務所の解決事例
- 当事務所のIT業界労務特化コンサルティング
取扱分野
ご相談のご予約はこちらから



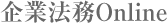
-300x72.png)

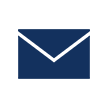 でのお問い合わせは
でのお問い合わせは